
目次 Contents
何気ない通勤も気温が氷点下になると道路の路面は凶器となること、ご存知でしょうか。
1年のうち12月中旬から3月下旬ごろまでは、毎朝バイクを運転されている方は注意が必要です。
気温だけ気にしていても実は、雨の場合も気をつけなければいけないのです。
季節を問わず1年中気をつけねばならないのは、雨です。
雨と、凍結、道路には危険箇所が多数ありますので、一つずつ理解して事故に繋がらないよう認識していただけたらと思います。
道路の危険箇所
路面状態を知る
摩擦係数をご存知でしょうか、(単位:μ)ミューという単位を用いて路面の滑りやすさを示すものです。
乾燥したコンクリート(ドライ状態):0.85~0.75μ。
雨の場合コンクリート(ウエット状態):0.7~0.6μに下がる。
乾燥したアスファルト(ドライ状態):0.8~0.75μ。
雨の場合アスファルト(ウエット状態):0.6~0.45μに下がる。
砂利道:0.5μ。
濡れていない鉄板(ドライ状態):0.8~0.4μ。
雨の場合の鉄板(ウエット状態):0.5~0.2μに下がる。
雪路:0.5~0.35μ。
圧雪路:0.35~0.2μ。
氷結路:0.2~0.07μ。
雨の日は、通常(ドライ)の日よりも摩擦係数が下がり、停めようとブレーキを踏んでも制動距離が倍近くなるのを認識しておきます。
ですから事故が多い日は、雨、そして雨と夜間が足されると事故率が増える。(5倍~7倍といわれてます)
滑る箇所(雨の場合)
1.工事中の道路上に敷かれた鉄板(クレーン、ダンプ、工事区間)。
2.マンホールの上フタ(上記画面が一例です)。
3.横断歩道(白線と白線の間に雨水が溜まる)。
4.白線と黄色線 上の線(センターライン、車道線)。
5.橋げたのつなぎ目(ギザギザした鉄の部分)。
6.側溝。(排水フタ)。
7.台風や強風時に落ちる葉。
8.秋~冬にかけて落ちる落ち葉(地面を覆う箇所)。
9.車両から落ちて路面に広がる油跡。
10.工事車両から落ちて広がる小石。(カーブ、交差点が多い)
このような場所は、二輪車(バイク、スクーター)は気を使いながら走ることです、もちろん、スピード、車間距離。
四輪車は、速度を落とし、車間距離を多めにとります。
滑る箇所(冬の朝、凍結の場合)
1.雨の場合の(1~10)項目全て。
2.前日が雨、水溜り箇所が凍る場所。(道路で言えば窪んでいるところとなります)
3.前日が雨、日差しが出ても日が当たらない場所。(朝だけでなく昼間であたらない場所もあります)
4.陸橋(地面と離れている箇所全エリア、二輪、四輪含めて滑る)。
5.橋(橋の入口から出口まで全域、特に中央部分が凍結、二輪、四輪も含めて滑る)。
四輪ならスリップ事故、二輪なら転倒事故に繋がります。
特に多いのは、橋の上、陸橋が多いのです。
6.日ごろから濡れている箇所。
7.道路の凍りコブ(いつコブが発生しているのか分からないのが恐ろしい)

雪が降った後に、必ずアスファルトに出てくるのが、「氷のコブ」です。
やっかいなのは、硬くてどこでも発生するのです。
原因は、
・前日の雪が積もり車の自重にて踏まれ硬くなり、ひどい場合は50m以上あります。
・車の屋根から雪が落ちる場合、トラックのある一部分残雪部分から落ちる場合があり、落ちた雪はタイヤで踏みつぶされコブが発生します。
・歩道を雪かきされた方が、道路に投げる場合、投げ入れた雪がタイヤに踏み潰されコブの発生。
・雪国に運送した大型トラックが残雪を落とし、次の車、トラックが雪を踏み固めコブの発生。
原因はもっとあると思いますが、この氷のコブにバイクが乗ると、転倒の恐れが大です。
朝でも昼でも夜でも、このコブは場所を関係なく発生しているので大変危険です。
対処法は?
車間距離を保ち、氷のコブを早く見極め、左右に移動できるくらいのスピードを保つことぐらいしかないと思います。
コブに乗り上げてから、左右に重心を移動すると転倒、その場合はブレーキもかけず、エンジンブレーキだけでなるべく直進する方向へ切り替えなければなりません。
もちろんスピードの出し過ぎでは、効果はないはず。
氷のコブは、雪が降っていなくても、雪国へ行ったトラックが落とすものと認識して3月までは道路に気配り必要です。
8.雪解けしたアイスバーン
雪が降った後、どこでも雪かきすると思いますが、山になっている光景を頭に浮かべてください。
日中に溶け出し山は少しづつ小さくなってゆきますが、解けた雪解け水はすぐに排水されればよいのですが、場所により道路へはみ出して水溜りになっている場合があります。
夜になると、水溜りは氷ついてアイスバーンへ変身するのです。
アイスバーンになれば、バイク・車もすべてスリップします。
対処法は、こちらも同じく車間距離とスピードです。
車間距離をとらないと車は通過できましたが、2輪の場合はそうはいかなく転倒します。
アッ!と思ったとき減速し直進するか、左右どちらかにアイスバーンが途切れているという判断ができる車間距離とスピードが転倒防止となります。
こちらを読んで記憶に留めていただければ、事故は防げるはずです。
二輪車の考え方として、自動車が普通に通れたから安心と思わないで下さい、自動車の通ったタイヤ跡(わだち)だけが溶けているだけなので、すり抜けをしようとするれば転倒し停止中の自動車にぶつかります。
道路の路面が太陽光に照らされてキラキラと光っている、日陰の部分になると路面は白く覆われているような状態です。
路面の凍結は気温が何度くらいからなのか
冬の朝は凍結しやすく、夕方や夜は凍結しづらい。
普段乗りなれた通勤道路も朝だけは注意して走ることが大切です。
一般的には、気温-3℃で凍結しやすく、3℃で凍結路面が解凍しはじめるようです。
(条件にもよりますので1℃~3℃でも凍結する場合があります)
凍結路面に出くわしたら対処法
1.急ハンドルはしない。
2.急ブレーキはしない。
3.急加速はしない。
以上を守ることです、どれかをすると滑ります。(やはりアクセルを緩めることが必要です)
凍結の疑いがある朝、注意して運転する方法
1.滑りやすい場所と思われる場所はスピードを落として走行する。
2.タイヤロックを防ぐため、早めのブレーキで対応する。
3.前方の車といつもより車間距離をとる。
4.カーブでは、二輪も四輪も荷重が移動するので、減速し急ハンドルせずゆっくり曲がる。
5.上り坂は、高めのギア、アクセルは踏み込まず、ゆっくりのぼります。
6.下り坂は、エンジンブレーキを利用して、スピードが上がらないようにします。
路面の凍結防止剤の効果
凍結防止剤を見たことはあると思いますが、白い粒状のものが、交差点、橋、陸橋にまかれています。
塩化カルシウム、塩化ナトリウムがまかれています。
塩は、雪を溶かす、凍らせない効果がありますが、いつもまかれていると信じてはいけまんせん。
まいてあったり、まかれてなかったり日々の散布状態はわかりませんので、まかれていない状態で常に走る心がけが必要です。
自分の車、バイク、スクーター自主点検
路面ばかりに気をつかっていても、自分の愛車が適性でないと、転倒事故、スリップ事故につながります。
1.空気圧は適正でしょうか。
2.タイヤの溝は、適正でしょうか。
3.二輪の場合、荷物など積んでいる場合左右のバランスがとれているでしょうか。
4.ブレーキは、適正でしょうか。
5.オイルのにじみ、漏れなどはないでしょうか。
忘れがちなのは、空気圧、タイヤの溝です、オイル漏れは深刻です、万が一オイルが車輪を伝わりタイヤに付いた場合は、二輪車の場合は転倒しますから、外観目視でよいので、前輪の周辺、後輪の周辺を見てください。
あと、駐車スペースがコンクリートやアスファルトなら停車中の朝、コンクリートを見れば、オイルが垂れた跡が見えるはずです。
冬の朝は朝日が昇るのが遅いかもしれませんが、是非確認して下さい。
おわりに
凍結や滑る道路をご理解いただけたでしょうか。
また2輪の転倒防止や事故防止(2輪、乗用車)含めて防ぐ方法(危険予知)もご理解していただけたと思います。
本来なら、朝の日の出前は道路を走ることは危険だと誰もが感じていると思います。
会社に遅れる、間に合わないという気持ちがあるといつものようにアクセルを開き、スピードを上げ、コントロールを失い事故、巻き添え事故になると思います。
事故が発生する原因は、心のコントロールが必要かもしれません。
事故が起きた場所を数日後に通ると、花束が置かれていると心が痛くなる重いです。
くれぐれも、冬の凍結期間は、ゆとりをもった走り方で冬を乗り切りたいと思います。
対向車のスリップ巻き添えも考えられます、冬の朝と雨の日は緊張しながらの運転が望ましいので注意しながら、事故のない運転を目指しましょう。
関連記事
→ミネラルは体内で作ることができない 毎日の食事からとる必要性があります
→歯槽膿漏 40歳過ぎたら80%の方が歯周病で歯が抜けるので注意
→こどもの国横浜 あそびの中に未来がある 2017年9月10月のイベントと各施設のお得情報
→江ノ島 観光やデート知っ得損なし情報!(駐車場・トイレ・喫煙)
→箱根の黒卵 観光前に知っておく 耳寄り情報!(駐車場・喫煙)
→アクセスアップ塾in淵野辺セミナー初めて参加!素人でも問題なし
コメント
-
2017年 9月 27日
-
2017年 11月 12日



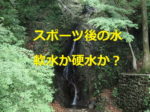



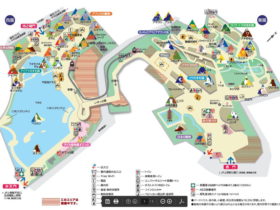
この記事へのコメントはありません。