
目次 Contents
ミネラルは、食べ物からとる必要があります。
口に入れるものから摂取されます。
人間の体内では作れない。
ミネラルの必要性
体の骨など組織構成、体の調子を整える働きがある。
ミネラルは体の約4%が構成に必要な部分で、残りの約96%が炭素、水素、酵素、窒素で人体は構成されている。
(炭素、水素、酵素、窒素以外はミネラル)
ミネラルというのは、約110種類の金属元素の総称です。(例えば、カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛、銅など)
怖いのは、人間はミネラル無しでは生存が不可能と言われております。
さらに怖いのは、現代の野菜と穀物はミネラルが減少してきていること。
(繊維質、砂糖、小麦、塩は精製過程で除去されている)
必要なミネラルは、主要7種と微量9種のあわせて16種類、ミネラルを日々摂取する必要があります。
主要7種類のミネラル(ナトリウム、マグネシウム、リン、イオウ、塩素、カリウム、カルシウム)
微量9種類のミネラル(クロム、マンガン、鉄、コバルト、銅、亜鉛、セレン、モリブデン、ヨウ素)
不足がちなもの
・(主要7種類)カルシウム:(骨粗しょう症になる可能性)
・(微量9種類)鉄:(貧血を起こす可能性)
とりすぎ
・(主要7種類)ナトリウム:(高血圧、脳卒中、生活習慣病)
ミネラルの種類と多く含んでいる食品例と摂取量
1、(主要1/7種類) ナトリウム:食塩、しょうゆ 「男性:8.0g未満、女性7.0g未満」。
2、(主要2/7種類) マグネシウム:豆類、種実類、海藻類、魚介類「男性:370mg未満、女性:290mg未満」。
3、(主要3/7種類) リン:魚介類、牛乳・乳製品、豆類、肉(ビタミンDで吸収効果が上がる)「男性:3,000mg未満、女性:3,000mg未満」。
4、(主要4/7種類) イオウ:牛肉、大根、ニラ、玉ねぎ、牛乳、小麦粉「摂取基準は特にない」。
5、(主要5/7種類)塩素:塩化ナトリウムと塩化カリウムとして存在「摂取基準は特にない」。
6、(主要6/7種類)カリウム:果物、野菜、芋、豆類、干物(ビタミンDで吸収効果が上がる)「男性:3,000mg未満、女性:2600mg未満」。
7、(主要7/7種類)カルシウム:牛乳・乳製品、小魚、海藻類、大豆製品、緑黄色野菜「2,500mg未満、女性2,500mg未満」
8、(微量1/9種類)クロム:魚介類、肉類、卵、チーズ、穀類、海藻類「男性:10μg、女性:10μg(ミューグラム)」。
(1mg=1000μg、mgの1/1000がμgとなります)
9、(微量2/9種類)マンガン:穀類、豆類、種実類、小魚、豆類「男性:11mg、女性:11mg」。
10、(微量3/9種類)鉄:海藻類、貝類、レバー、緑黄色野菜(ビタミンCで吸収効果が上がる)「男性:7.5mg、女性10.5mg(月経あり)、女性:6.5mg(月経なし)。
11、(微量4/9種類)、コバルト:主にビタミンB群とともに働く。
12.(微量5/9種類)、銅:レバー、魚介類、種実類、豆類、ココア「男性:1mg、女性:0.8mg」。
13、(微量6/9種類)、亜鉛:魚介類、肉類、穀類、種実類「男性:40mg未満、女性:35mg未満」。
14、(微量7/9種類)、セレン:魚介類、肉類、卵「男性:30μg、女性:25μg」。
15、(微量8/9種類)、モリブデン:豆類、穀類、レバー「男性:30μg、女性:25μg」。
16、(微量9/9種類)、ヨウ素:海藻類、魚介類「男性:130μg、女性:130μg」。
ここで考えられることは、普段からスーパーで見かけるものばかりです。
偏らず、まんべんなく食すればミネラルが自然と入ることが判断できます。
各ミネラルの詳細
1、(主要1/7種類) ナトリウム:体の中に体重の約0.15%含まれる。
醤油や味噌などを食べる日本人には摂取量が大切です。
2、(主要2/7種類) マグネシウム:体内に20~25g存在。
血圧を下げる、神経の興奮を鎮める。
ストレスが多いと消費されるので、精神面の軽減には積極的に摂り入れる。
3、(主要3/7種類) リン:体内に約780g含まれている。
骨や歯を作り、細胞の中に存在している。
添加物の過剰摂取で多量になる場合があります。
4、(主要4/7種類) イオウ:摂取基準がない、たんぱく質を摂取していれば自然と摂取しているため。
たんぱく室(肉類・魚介類・卵類・大豆類・乳製品)。
5、(主要5/7種類)塩素:食塩に含まれている。
胃酸の成分、肝臓機能を助けます。
6、(主要6/7種類)カリウム:体内に体重の約0.2%含まれています。
塩分の排出を促します、各細胞の水分量を調整します。
くだもの、野菜が採りやすい。
7、(主要7/7種類)カルシウム:体重70kgあたり、1,000gあり、体に最も多く含まれる。
骨や歯を構成、精神面も落ち着かせる作用もある。
日本人には不足がちです。
8、(微量1/9種類)クロム:体の中に約2mg含まれています。
高血糖、高脂血症、動脈硬化の予防になります。
不足することはほとんどない微量ミネラルです。
9、(微量2/9種類)マンガン:体の中に約12mg含まれています。
インスリンの合成を助け、糖尿病を予防します。
野菜や果物、豆類、ナッツに含まれています。
10、(微量3/9種類)鉄:体の中に約3~4g含まれています。
貧血を予防し肝臓の解毒作用があります。
月経がある女性には、多めに摂取したい鉄ミネラルです。
11、(微量4/9種類)、コバルト:摂取基準がありません。
血液をつくると言われています。
ビタミンB12を採れば、自然と摂取しております。
(ビタミン12:しじみ、あこがい、すじこ、牛レバー、あさり、いくら、はまぐり佃煮、鶏レバー、豚レバー、たらこ)
12.(微量5/9種類)、銅:体の中に約80~100mg含まれています。
鉄をサポートし、銅がないと赤血球がうまく合成されません。
貧血予防、紫外線から身を守ります。
13、(微量6/9種類)、亜鉛:体の中に約2g含まれています。
味覚機能を調整します、成長障害や味覚障害を亜鉛が不足な場合起こります。
中毒を起こすおそれがあるので多量に摂取しないこと。
14、(微量7/9種類)、セレン:体の中に約10mg含まれています。
主体は肝臓、腎臓、抗酸化作用により老化防止、細胞を若々しく維持する。
免疫力の向上。
15、(微量8/9種類)、モリブデン:体の中に約9mg含まれています。
尿が不要になった場合に老廃物を尿酸に変えるミネラルです。
16、(微量9/9種類)、ヨウ素:体の中に約10mg含まれています。
甲状腺に存在、皮膚や髪の健康維持するためのミネラルです。
細胞の代謝を上げる作用。
長寿年齢(2017年3月1日)厚生労働省(第22回生命表)。
男性:80.75歳。(過去最高)
女性:86.99歳。(過去最高)
25年間の間で、男性は4.83歳、女性は5.09歳伸びている。
明治時代に始まった生命表では、(明治24~31年)での平均寿命、男性は42.8歳、女性44.3歳であった。
平均寿命は年毎に伸びており、2060年には、内閣府公表によると男性84.19歳、女性90.93歳までなると予測されている。
都道府県の長寿ランキング1位~3位(厚生労働省2010年)。
1位、男性:80.88歳(長野県)、女性:87.18歳(長野県)。
2位、男性:80.58歳(滋賀県)、女性:87.07歳(島根県)。
3位、男性:80.47歳(福井県)、女性:87.02歳(沖縄県)。
神奈川県は、男性:80.25歳で5位、女性:86.63歳で15位。
東京都は、男性:79.82歳で14緒、女性:86.39歳で22位。
ワースト1位、男性:77.28歳(青森県)、女性:85.34歳(青森県)
なんと長野県が男女とも1位です。
調べて見ますと、昭和40年代の長野県は脳卒中の死亡率全国ワースト1位でした。
それが長寿県、長野県となり原因を探ると、「減塩活動運動」があったということです。
野沢菜などの保存食をはじめ、減塩に対する県民の皆様が努力された結果、長寿県となったのです。
ワースト1位の青森県では、今後減塩に対する考え方を切り替える必要もあるし、私たちも減塩という言葉を受け入れるッ必要があると考えられます。
ここでミネラルに戻りますが、この減塩をすること、つまり精製塩を使った食べ物ではナトリウムのミネラルが摂取できず、自然塩の塩を摂りいれれば、ナトリウムのミネラルが摂れます。
(精製塩:ミネラルを化学的に除去して作られるもの、約95.5%が塩化ナトリウム、ミネラルはほとんどありません)
おそらく、長野県の皆様は天然塩を使い(ミネラル含む)減塩に対応したと思います。
昔は、沖縄県が長寿1位で有名でした、ここ最近のデーターでは、男性30位、女性3位まで落ちてしまいました。
原因は不明ですが、食の欧米化がすすみファストフード食があげられております。
加工食品の摂り過ぎが順位を落としたと言われております。
朝・昼・夕の食事メニュー(例)
朝、ビタミン、ミネラルを含んだ野菜、フルーツを摂る事。
昼、白米・玄米など炭水化物を撮ること。(エネルギー摂取)パスタやパンでは、精製された小麦粉からなので、太りやすいし、糖質も高めとなってしまうのです。
夜、魚介類、納豆、豆腐など大豆製たんぱく質を摂る。(良質な植物性たんぱく質)
牛肉、豚肉、鶏肉からもたんぱく質は摂れますが、食べ過ぎると悪玉菌が増える可能性があります。
野菜を採る。
間食はしない。
ミネラル不足の原因
ミネラル不足の原因は日本人なら土に原因があるようです。
そうなのです、日本の土壌は欧米に比べるとミネラル分が少ないと言われております。
島国であること、度重なる農薬、化学肥料の使用で野菜など作られていますが、現実は土とミネラルがこれらの肥料、農薬によりバランスが崩れ昔に比べるとミネラルが低下しているのです。
ではどうしたらミネラルを補給できるのか?
ミネラル補給にふさわしい食材
食材は、海産物を積極的にとること。(ワカメ、昆布、ひじき、海苔、海藻類)
飲み物は、ミネラルウォーター、スポーツドリンクです。
おわりに
ミネラルは体内でつくることができないもの、口からとりいれて体内補給するものが少しご理解していただければ幸いです。
普段からスーパーで購入する食べ物をバランスよく摂取していれば、ミネラル不足にならないと思います。
塩分の部分にも触れましたが、自然塩を使いミネラル補給し、減塩すれば健康への第一歩が開けるかもしれません。
毎日からミネラルを採る必要性をご理解していただけたでしょうか。
健康関連記事
コメント
-
2017年 9月 25日トラックバック:血圧が高い方 高血圧を理解し予防対策 | Tami(多観)
-
2017年 9月 27日
-
2017年 10月 22日
-
2017年 10月 23日トラックバック:火の大切さを知っておく | Tami(多観)
-
2017年 10月 26日トラックバック:災害時に火をおこして生きて行く3日間グッズ | Tami(多観)
-
2017年 10月 30日
-
2017年 11月 08日
-
2017年 11月 10日
-
2017年 12月 02日
-
2017年 12月 02日
-
2018年 2月 04日







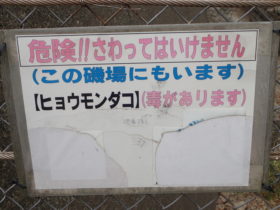
この記事へのコメントはありません。